「出雲大社と伊勢神宮は仲悪い」という噂を耳にしたことはありませんか。日本を代表する二つの神社について、本当に仲が悪いのか、その関係はどうなっているのか、とても気になりますよね。
この記事では、両社の関係性を深く理解するために、日本神話における国譲りの逸話から、格式ではどっちが上なのか、そして伊勢神宮と出雲大社の違いを簡単に解説します。
さらに、なぜ天皇は出雲大社に入れないと言われるのか、日本の三大神社として伊勢神宮と出雲大社に並ぶあと1つはどこなのか、両方参拝する際の注意点まで、様々な角度からその真相に迫ります。
出雲大社と伊勢神宮は仲悪い?噂の歴史的背景

日本神話から読み解く両社の起源
伊勢神宮と出雲大社の関係性を理解する上で、日本の神話を記した『古事記』や『日本書紀』の知識は欠かせません。この二つの神社は、それぞれ日本神話における中心的な神様を祀っており、その物語が両社の立ち位置を決定づけています。
まず、伊勢神宮に祀られているのは、太陽を司る女神であり、皇室の祖先神(皇祖神)とされる天照大御神(あまてらすおおみかみ)です。天照大御神は、神々が住む天の世界「高天原(たかまがはら)」を治める最高神として描かれています。このため、伊勢神宮は日本の全神社の頂点に立つ、別格の存在とされています。
一方、出雲大社のご祭神は、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)です。大国主大神は、地上世界である「葦原中つ国(あしはらのなかつくに)」を豊かな国に造り上げた、国造りの神様として知られています。多くの困難を乗り越え、様々な神々と協力して国土を開拓した英雄的な神様です。

つまり、天照大御神が「天」を代表する神様、大国主大神が「地」を代表する神様ということだね
なるほど。そう考えると両社の役割の違いがイメージしやすいわね

このように、伊勢神宮は天上の神々の世界、出雲大社は地上の世界と、それぞれが神話の中で重要な舞台を担っています。両社の関係は、この天と地の神々の物語、特に後述する「国譲り」によって決定的なものとなるのです。
国譲りの物語に秘められた力関係

「出雲大社と伊勢神宮は仲が悪い」と言われる最大の要因が、「国譲り」の神話です。これは、大国主大神が苦労して造り上げた地上世界(葦原中つ国)を、天照大御神の子孫に譲り渡すという物語です。
物語の概要はこうです。天照大御神は、地上世界は自分の子孫が治めるべきだと考え、大国主大神のもとへ使者を送ります。何度かの交渉の末、最終的に武力の神である建御雷神(たけみかづちのかみ)が派遣され、大国主大神に国を譲るよう迫りました。
大国主大神はこれを受け入れますが、その条件として「自分の住処として、天の神の御子が住むのと同じくらい、柱を太く、天に届くほど高く壮大な宮殿を建ててほしい」と要求しました。この時に建てられた壮大な宮殿が、現在の出雲大社の起源とされています。
国譲りのポイント
- 統治権の委譲:大国主大神は、目に見える世界の政治(顕事・あらわごと)の統治権を天の神(天孫)に譲った。
- 新たな役割:その代わり、大国主大神は目に見えない世界(幽事・かくりごと)、特に人々の縁を結ぶなど、神事や精神的な世界を治める役割を担うことになった。
この物語は、一見すると出雲が伊勢に力で屈服し、国を奪われたように見えるため、「両社には確執があるのではないか」という憶測を生む原因となりました。しかし、見方を変えれば、これは単なる支配関係ではなく、政治と祭祀の役割分担を定めたものと解釈することもできます。
大国主大神は統治権を譲る代わりに、神事を司るという非常に重要な役割と、壮大な社殿を手に入れたのです。この複雑な力関係が、両社の独特な関係性の基礎となっています。
伊勢神宮と出雲大社の違いを簡単に解説

伊勢神宮と出雲大社って具体的に何が違うのかしら?
では、両社の特徴を簡単な表で比較してみましょう

| 項目 | 伊勢神宮 | 出雲大社 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 神宮 | 出雲大社(いづもおおやしろ) |
| ご祭神 | 天照大御神(あまてらすおおみかみ) | 大国主大神(おおくにぬしのおおかみ) |
| ご利益 | 国家安泰、皇室の繁栄、国民の幸福 | 縁結び、五穀豊穣、商売繁盛 |
| 建築様式 | 唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり) | 大社造(たいしゃづくり) |
| 参拝作法 | 二礼二拍手一拝 | 二礼四拍手一拝 |
| 式年遷宮 | 20年に一度(常若の思想) | 不定期(約60~70年に一度) |
| 神様の集い | - | 神在月(旧暦10月)に全国の神々が集まる |
特に大きな違いはご利益です。伊勢神宮は公的な性格が強く、国家の平和や国民全体の幸福を祈る場所とされています。
このため、正宮では個人的なお願い事をするのではなく、日々の感謝を伝えるのが良いとされています。個人的なお願いは、内宮の別宮である荒祭宮(あらまつりのみや)で行うのが慣例です。
一方、出雲大社は国譲りの神話に基づき、縁結びをはじめとする人々の個人的な願い事を司る場所とされています。また、参拝作法が「二礼四拍手一拝」と特殊なのも大きな特徴です。これは、大切な祭事の際に八拍手をするなど、古くからの伝統作法が受け継がれているためと言われています。
あわせて読みたい
神社の格式では結局どっちが上?
神社の格式について話すとき、「伊勢神宮と出雲大社ではどっちが上なのか」という疑問は多くの人が抱くところです。結論から言うと、最も格式が高いとされるのは伊勢神宮です。
神社には「社号(しゃごう)」という称号があり、一般的に「神宮」「宮」「大社」「神社」などの順で格式が高いとされています。伊勢神宮の正式名称は、地名を冠さないただの「神宮」です。これは、伊勢神宮が他のいかなる神社とも一線を画す、唯一無二の特別な存在であることを示しています。

神社の中でも伊勢神宮だけは別格というのはやっぱりあるよね
社格制度の歴史
明治時代に定められた近代社格制度では、神社は国が管理する「官社」とそれ以外の「諸社」に分けられました。伊勢神宮はこの社格制度の枠外に置かれ、すべての神社の上に立つ最高位の存在と位置づけられていました。
この制度は戦後に廃止されましたが、現在でもその序列意識は人々の間に根強く残っています。
一方、出雲大社は「大社」という社号を持ちます。もともと「大社」といえば出雲大社のことだけを指す固有の呼び名でしたが、明治以降、他の神社も「大社」を名乗るようになりました。

昔は出雲大社だけしか大社とつく神社はなかったのね
それでも、出雲大社は国つ神(地上の神)のトップを祀る神社として、伊勢神宮に次ぐ非常に高い格式を持つ別格の存在であることに変わりはありません。
伊勢神宮が「天の神のトップ」を祀る神社、出雲大社が「地の神のトップ」を祀る神社と考えると、単純な上下関係ではなく、それぞれの領域で最高位の神社と理解するのが良いでしょう。
日本の三大神社は伊勢神宮と出雲大社あと1つは?
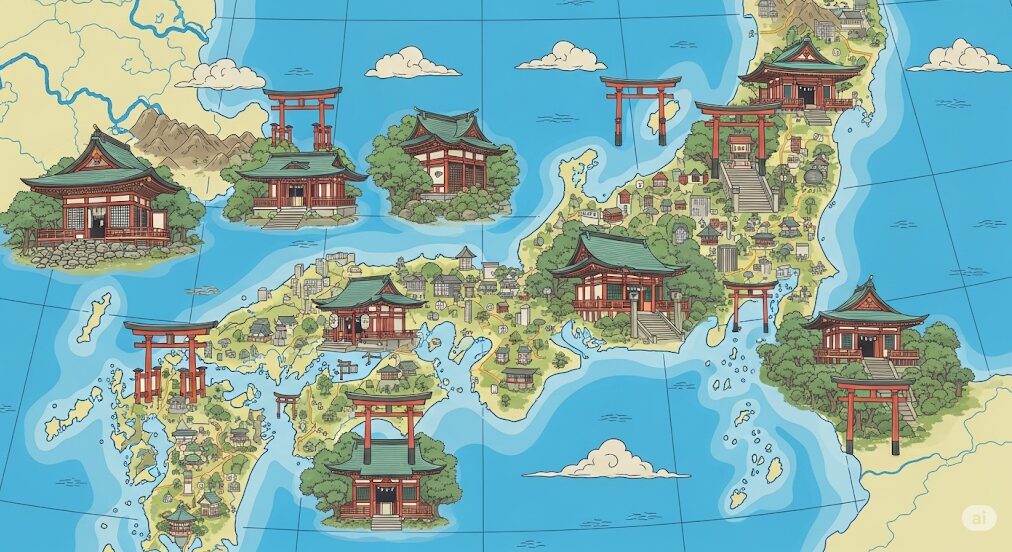
「日本の三大神社」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。多くの場合、伊勢神宮と出雲大社は必ず数えられますが、あと1つはどこかについては、実は明確な定義がなく、いくつかの説が存在します。
歴史的な文献に基づいて、主に二つの説が挙げられます。
1. 日本書紀に基づく説
奈良時代に成立した日本最古の正史『日本書紀』に重要な神社として登場することから、以下の三社が挙げられることがあります。
- 伊勢神宮(三重県)
- 出雲大神宮(京都府)※出雲大社(島根県)とする説もある
- 石上神宮(いそのかみじんぐう・奈良県)
この説では、島根の出雲大社ではなく、京都の出雲大神宮が挙げられることがあります。出雲大神宮は「元出雲」とも呼ばれ、非常に古い歴史を持つ神社です。
2. 延喜式神名帳に基づく説
平安時代にまとめられた神社の一覧『延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)』で、当時最も格式が高い「神宮」の称号を与えられていた三社を指す説です。
- 伊勢神宮(三重県)
- 鹿島神宮(かしまじんぐう・茨城県)
- 香取神宮(かとりじんぐう・千葉県)
「日本三大神社」という括りは、後世になって作られたものであり、公式に定められたものではありません。どの説が正しいというわけではなく、何を基準にするかによって変わる、と理解しておくのが良いでしょう。
いずれにせよ、伊勢神宮と出雲大社が日本の神社の中で極めて重要な位置を占めていることは、どの説においても共通しています。

文献によっても変わるし、人によって3大神社は変わるものかもしれないね
鹿島神宮や香取神宮が入るって少し意外ね。あなたにとっての3大神社はどこですか?

出雲大社と伊勢神宮が仲悪い説の真相とは

なぜ天皇は出雲大社に入れないのか
「天皇は出雲大社に入れない」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは完全に正確な情報ではありません。
正しくは「天皇陛下は出雲大社の御本殿の最も奥深く、ご神体が鎮座する神聖な空間にはお入りにならない」という慣例がある、ということです。
この背景には、やはり「国譲り」の神話が深く関わっています。前述の通り、国譲りによって、天照大御神の子孫である天皇は「顕事(目に見える世界の政治)」を、大国主大神は「幽事(目に見えない神事や縁結び)」を司ることになりました。

ここにも日本神話が関わってくるんだね
神話を知らない人も増えてるけど、日本神話は切っても切れない関係なのね

役割分担の尊重
天皇陛下が出雲大社の最も神聖な場所に入らないのは、この神話に基づく役割分担を尊重し、大国主大神の領域に過剰に立ち入らないようにするという、深い敬意の表れと解釈されています。
これは、出雲大社を軽んじているのではなく、むしろその神聖性を最大限に尊重しているからこその慣例なのです。
実際には、天皇陛下や皇族方が勅使を派遣されたり、御本殿の外にある拝殿で拝礼されたりすることはあります。決して出雲大社への参拝が禁じられているわけではありません。
この「入れない」という言葉が一人歩きし、天皇家と出雲大社の対立の象徴のように語られることがありますが、その本質は互いの神聖な領域を尊重し合う、日本の古来からの精神性に基づいているのです。
両方参拝する際の順番や注意点

伊勢神宮と出雲大社、両方の神社に参拝したいと考える方も多いでしょう。もちろん、両方参拝することに何の問題もありません。ただし、それぞれの神社の格式や由緒を理解し、敬意を払って参拝することが大切です。
両社を参拝する上で、厳格な順番の決まりはありませんが、古くからの慣習や考え方に基づいたおすすめの順番は存在します。
一般的な考え方
伊勢神宮は皇室の祖先神を祀る公的な性格の強い神社であるため、先に伊勢神宮で日本全体の平和や日々の感謝を捧げ、その後に個人のご縁などを願って出雲大社に参拝するという流れが、筋が通っていると考える人が多いようです。
伊勢神宮内の参拝順序
伊勢神宮に参拝する際は、「外宮先祭(げくうせんさい)」という習わしに従い、まず豊受大御神を祀る外宮(げくう)を参拝してから、天照大御神を祀る内宮(ないくう)へ向かうのが正式な作法です。
両方参拝する際の注意点
- 気持ちの切り替え:伊勢神宮では公的な感謝を、出雲大社では個人的な願いを、というように、それぞれの神社の性格に合わせてお祈りする内容を意識すると良いでしょう。
- 作法を守る:前述の通り、伊勢神宮は「二礼二拍手一拝」、出雲大社は「二礼四拍手一拝」と作法が異なります。それぞれの神社の作法を事前に確認し、正しく行いましょう。
- 時間に余裕を持つ:両社は地理的に離れているため、移動には時間がかかります。慌ただしい参拝にならないよう、ゆとりを持った計画を立てることが大切です。

順番にこだわりすぎる必要はありませんが、それぞれの神社の背景を理解し、心を込めて参拝することが最も重要です
心を込めて参拝する。やっぱりそこに行きつくのよね

現代における皇室との関係性

歴史的には複雑な背景を持つ伊勢神宮(天皇家)と出雲大社ですが、現代における関係は非常に良好であり、むしろその結びつきは深まっていると言えます。
その象徴的な出来事が、2014年の高円宮家の典子さまと、出雲大社宮司の長男である千家国麿(せんげくにまろ)さんのご結婚です。典子さまは天皇陛下のいとこにあたります。
天照大御神の子孫である皇室と、大国主大神の子孫である出雲国造家(いずもこくぞうけ)が、結婚という形で結ばれたのです。これは、まさに現代における「国譲り」の融和を象徴する出来事として、大きな話題となりました。
このご結婚は、古代から続く両家の歴史的な関係性が、対立ではなく、尊重と協力のもとに続いていることを示しています。
また、天皇陛下が即位後に行う重要な儀式「大嘗祭(だいじょうさい)」では、出雲国造が神聖な火を起こすための道具を献上するなど、現在でも儀式を通じた深い関わりが続いています。
これらの事実からも、「仲が悪い」という噂は、あくまで過去の神話の表面的な解釈に基づいたものであり、現代の実態とは異なると言えるでしょう。
本当に仲が悪い?その関係は?
ここまで見てきたように、「出雲大社と伊勢神宮は仲が悪い」という説は、神話の一側面を切り取った解釈に過ぎず、現代の関係性においては正しくありません。
確かに、国譲りの神話や明治時代の祭神論争(神道の中心的な神様を伊勢の神とするか、出雲の神も加えるかで争った出来事)など、歴史上、両者が緊張関係にあった時期は存在しました。しかし、それは互いが日本の精神的支柱としての自負を持っていたからこその対立とも言えます。
現在の関係性のまとめ
- 役割分担:伊勢は「公」や「天」、出雲は「私」や「地」を司るという、互いに尊重し合うべき役割分担がなされている。
- 儀礼的な繋がり:天皇の即位儀礼などで、現在も出雲国造家が重要な役割を担っている。
- 血縁による結びつき:高円宮典子さまのご結婚により、皇室と出雲国造家は血縁でも結ばれ、融和の象徴となっている。
結論として、両社の関係は単純な「仲が良い・悪い」で語れるものではなく、日本の成り立ちに関わる、複雑で深く、そして尊い関係性であると理解するべきです。対立の歴史があったからこそ、現代の相互尊重に基づいた良好な関係が築かれているのです。
総括:出雲大社と伊勢神宮が仲悪いかの真相
この記事では、「出雲大社と伊勢神宮は仲が悪い」という説の真相について、多角的に解説してきました。最後に、記事の要点をまとめます。

日本の神社の奥深い物語に、ぜひあなたも触れてみてくださいね♪


