神社に関心を持ち始めた方の中には、御祭神の読み方や意味を検索して、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。御祭神の読み方や意味は、神社参拝をより深く理解するうえで欠かせない知識です。
本記事では、御祭神と主祭神の違い、御祭神と御神体の違いといった基礎的な情報から、御祭神の数え方、言い換え表現、さらには英語でどのように表現されるかまで丁寧に解説します。
また、代表的な御祭神一覧として、スサノオノミコトや天照大御神といった有名な神々にも触れ、各神社の信仰背景を理解する手助けとなる情報もご紹介します。
この記事を読むことで、御祭神という言葉に込められた意味が分かり、今後の神社巡りやご利益への理解が深まるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
御祭神の読み方と正しい意味とは

御祭神の読み方や意味を解説
御祭神は「ごさいじん」と読みます。神社について調べていると頻繁に出てくる言葉ですが、意外と正しい意味までは知られていないことがあります。
御祭神とは、神社に祀られている神様のことを指す言葉です。つまり、神社が対象として崇敬している存在の名称が「御祭神」になります。古くは自然崇拝の名残として山や川、岩などが神格化され、それが後に名前を持った神々として認識されるようになりました。
例えば、伊勢神宮では天照大御神(あまてらすおおみかみ)、出雲大社では大国主命(おおくにぬしのみこと)が御祭神として知られています。このように神社ごとに異なる神様が御祭神として祀られており、信仰の対象となります。
注意点として、神社に複数の神様が祀られている場合、すべての神を御祭神と呼ぶ一方で、最も中心的な神だけを指すこともあります。その場合は「主祭神」と区別して使われることが多いです。
神社を訪れる際には、どの神様が御祭神なのかを意識することで、その神社がどんなご利益に強いのかも理解しやすくなります。
御祭神と主祭神の違いを理解する
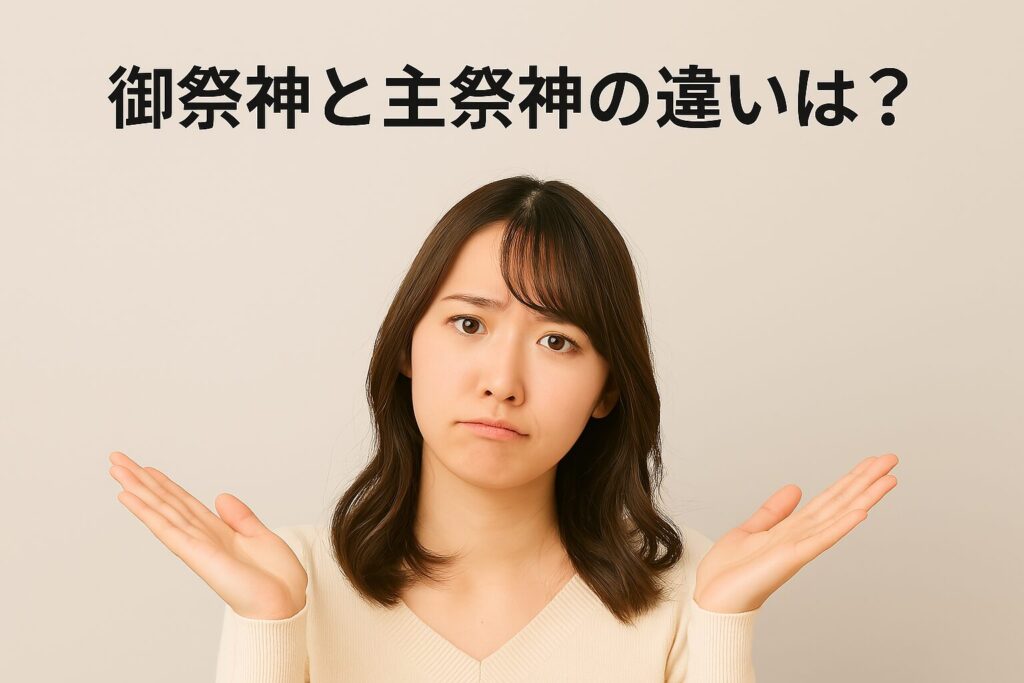
御祭神と主祭神は、どちらも神社に祀られている神様を指す用語ですが、意味と使い方には明確な違いがあります。
御祭神は神社全体で祀られているすべての神様を総称した呼び方です。一方で、主祭神(しゅさいじん)はその中でも特に中心的な存在として祀られている神様のことを意味します。
例えば、ある神社に三柱の神が祀られていた場合、その三柱すべてが御祭神ですが、その中でも最も重要とされる一柱が「主祭神」です。この主祭神は、神社の由緒や歴史、ご利益の内容に深く関係しています。
一方、主祭神以外に祀られている神様たちは「配神(はいしん)」や「相殿神(あいどのしん)」と呼ばれることもあります。これらの神々は主祭神と縁のある存在や、後に加えられた神様である場合が多く、同じ社殿で祀られていても立場には違いがあります。
混同しやすい用語ですが、それぞれの神社がどの神様をどのような立場で祀っているかを知ることで、信仰の背景をより深く理解できるようになります。
御祭神と御神体の違いとは

御祭神(ごさいじん)と御神体(ごしんたい)は、いずれも神社の信仰に関わる重要な存在ですが、意味と役割には明確な違いがあります。
まず御祭神とは、神社で祀られている神そのものを指す言葉です。人格や神格を持つ神様であり、その神に対して祈りを捧げたり、ご利益を願ったりする対象です。
一方、御神体は、その御祭神が宿るとされる「もの」や「場所」のことです。つまり御神体は神様の依代(よりしろ)であり、神が臨時的または恒常的に宿ると信じられている対象物です。鏡や剣、玉などが代表的で、山や岩、樹木といった自然物が御神体となっている神社も多く存在します。
例えば、伊勢神宮では天照大御神を御祭神とし、その神が宿る御神体として「八咫鏡(やたのかがみ)」が祀られています。このように、神様そのものが御祭神、そしてその神が宿る対象が御神体という関係になります。
注意すべき点として、御神体は神聖な存在であり、多くの神社では非公開です。神職であっても直接目にすることができないことがあり、それほど大切に扱われています。
御祭神の英語表現について
御祭神を英語で表現する場合、直訳が難しいため、文脈に応じて複数の言い方が使われます。一般的には「enshrined deity(祀られている神)」「enshrined god」や「Shinto deity(神道の神)」などが用いられます。
例えば、英語圏の神社案内文や観光資料では、「This shrine enshrines the deity Amaterasu Omikami.(この神社では天照大御神が祀られています)」のように説明されることが多いです。
一方、「御祭神」という言葉自体に神道特有の宗教的な背景があるため、必ずしも1語に変換できるわけではありません。状況によっては「divine spirit」や「sacred entity」といった、より抽象的な表現が適している場合もあります。
注意点として、宗教用語に関しては翻訳のニュアンスによって誤解が生まれることもあるため、観光や解説で使用する際には簡単な注釈や説明を添えるのが理想的です。日本文化を伝えるうえで、単語だけでなく背景まで丁寧に伝えることが求められます。
御祭神の数え方に決まりはある?
御祭神の数え方には特定の「ルール」があるわけではありませんが、日本語として数えるときには「柱(はしら)」という助数詞が使われます。これは神道において神を数える際に使う、特別な言い回しです。
例えば、「天照大御神一柱」「八百万の神々は無数の柱で表される」といったように使われます。柱という言葉には、神様が尊い存在であるという考え方が込められており、物理的な数え方とは異なる精神的な意味合いがあります。
この柱という単位は、神道の他の場面でも登場します。神様が何柱祀られているかによって、神社の規模や歴史的な背景を知る手がかりになることもあります。
ただし、現代では神様の数を「人数」や「体数」といった言葉で表現してしまう例も見られます。これは日常会話で使いやすいためですが、正式な場では「柱」を用いたほうが適切です。
神様を敬う心が言葉にも表れているのが、この数え方の特徴だといえるでしょう。
御祭神の読み方や意味を知って神社巡りを楽しく

御祭神の言い換え表現をチェック
御祭神を表す際の言い換え表現には、いくつかのバリエーションがあります。ただし、全く同じ意味ではなく、用いられる場面や意図によって微妙な違いがあるため、注意が必要です。
代表的な言い換えとしては、「祭神(さいじん)」があります。これは御祭神の丁寧語表現ではなく、より一般的かつ簡潔に神社に祀られている神を指す語です。神社の説明文や歴史書などでよく使われます。
他にも、「神様」や「神体の神」といった表現が会話の中では使われることもありますが、これはあくまで口語的なものです。文章中で正式に言及する場合は「御祭神」または「祭神」が無難です。
なお、「ご神体」と混同しやすいため、用語の選び方には注意が必要です。前述の通り、御神体は神が宿る対象物であり、神そのものを表す「御祭神」とは明確に役割が異なります。
このように言葉の選び方一つで神社に対する理解の深さが問われることもあるため、使い分けを覚えておくと安心です。
スサノオノミコトの御祭神としての特徴

スサノオノミコトは、神話の中でも非常に個性が際立つ神であり、御祭神としても多くの神社で祀られています。その最大の特徴は「厄除け」や「災厄を祓う力」に強いご利益があるとされている点です。
古事記や日本書紀に登場するスサノオノミコトは、天照大御神の弟神で、荒々しい性格と強大な力を持つ神とされています。ときに乱暴者として描かれることもありますが、それは自然の力の象徴としての側面でもあります。
最も有名な神話として、ヤマタノオロチという八つの頭を持つ大蛇を退治したエピソードがあります。この話から、スサノオノミコトは「邪を祓う神」「勇気と勝負運をもたらす神」として信仰されるようになりました。
また、ヤマタノオロチを倒したあとに櫛名田比売(くしなだひめ)と結婚したことから、縁結びや家庭円満の神としての信仰も広まっています。
御祭神としてスサノオノミコトが祀られている神社には、八坂神社(京都)や氷川神社(埼玉)などがあります。参拝することで災いを遠ざけ、運気を上げる後押しをしてくれるとされています。
天照大御神はどんな御祭神?

天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、日本神話において最も尊い存在のひとつであり、神道の中心的な御祭神です。その名が示す通り、太陽を象徴する神様であり、命の源としての役割を担っています。
この神様は、黄泉の国から戻った伊邪那岐命が禊を行った際に、左目を洗ったことで生まれたとされています。そして、高天原という天上の世界を統治するよう命じられました。
天照大御神は、農業をはじめとする生活の安定に関わる神として、国土の平和や五穀豊穣のご利益があるとされています。特に伊勢神宮(内宮)に祀られており、日本の皇室の祖神としても知られています。
その性格は穏やかで慈愛に満ちており、人々を温かく見守る存在とされています。一方で、岩戸隠れの神話のように、怒りや悲しみを表す場面もあり、非常に人間的な側面も持っています。
天照大御神を御祭神とする神社では、開運や家内安全、安産など、幅広いご利益を求めて多くの参拝者が訪れます。日本全国で非常に高い信仰を集めている神様です。
御祭神の一覧|代表的な神々
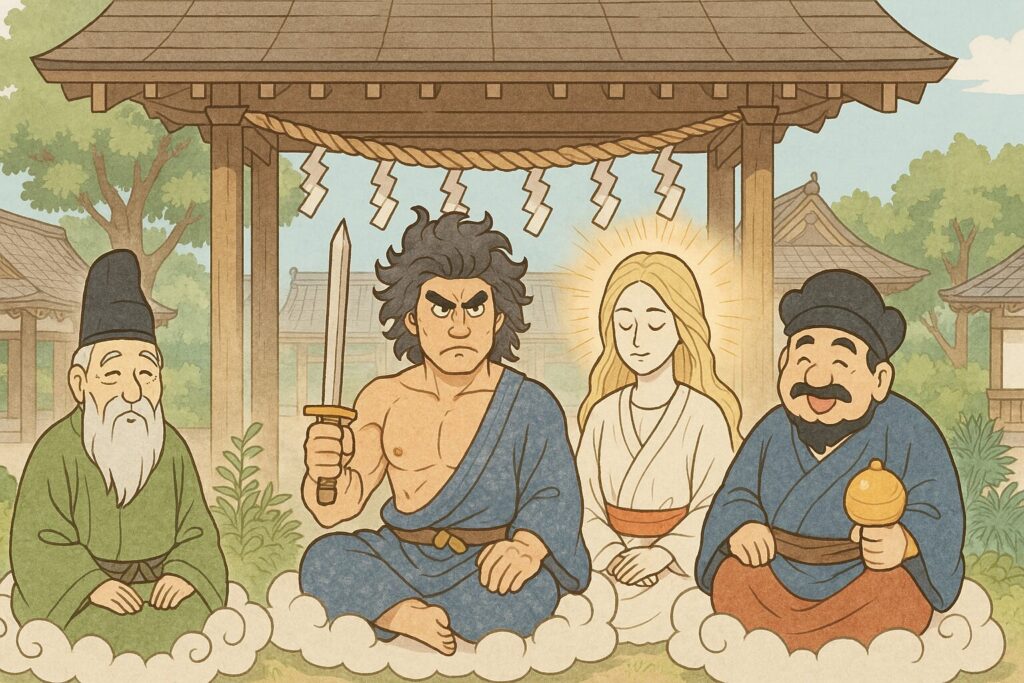
神社で祀られている御祭神は数多く存在し、その種類も非常に多彩です。ここでは、全国的に信仰を集めている代表的な御祭神を30柱ご紹介します。
天照大御神
- 読み方:あまてらすおおみかみ
- 誕生:伊邪那岐命が禊を行った際、左目から生まれた
- ご利益:国土安泰、五穀豊穣、開運、家内安全
- 主な神社:伊勢神宮(内宮)、天岩戸神社
須佐之男命
- 読み方:すさのおのみこと
- 誕生:伊邪那岐命の鼻を清めた際に生まれた
- ご利益:厄除け、災難除け、縁結び
- 主な神社:八坂神社、氷川神社、津島神社
大国主命
- 読み方:おおくにぬしのみこと
- 誕生:素戔嗚尊の子または子孫とされる
- ご利益:縁結び、商売繁盛、病気平癒
- 主な神社:出雲大社、大神神社
伊邪那岐命
- 読み方:いざなぎのみこと
- 誕生:天地開闢後に現れた神、国生み神話に登場
- ご利益:夫婦円満、子孫繁栄、厄除け
- 主な神社:多賀大社、伊邪那岐神社
伊邪那美命
- 読み方:いざなみのみこと
- 誕生:伊邪那岐命と共に国土を生んだ女神
- ご利益:安産、夫婦和合、生命力回復
- 主な神社:花窟神社、比婆山久米神社
菅原道真
- 読み方:すがわらのみちざね
- 誕生:平安時代の実在の人物、死後「天神様」として神格化
- ご利益:学業成就、合格祈願、文運上昇
- 主な神社:太宰府天満宮、北野天満宮
宇迦之御魂神
- 読み方:うかのみたまのかみ
- 誕生:食物を司る神、スサノオの子とも言われる
- ご利益:五穀豊穣、商売繁盛、家内安全
- 主な神社:伏見稲荷大社、豊川稲荷
少彦名命
- 読み方:すくなびこなのみこと
- 誕生:高皇産霊尊の子とされる国造りの神
- ご利益:医薬、酒造、温泉の神
- 主な神社:少彦名神社、服部天神宮
天児屋根命
- 読み方:あめのこやねのみこと
- 誕生:祝詞を司る神、天岩戸の神話に登場
- ご利益:学業成就、家内安全、出世開運
- 主な神社:春日大社、枚岡神社
事代主命
- 読み方:ことしろぬしのみこと
- 誕生:大国主命の子、漁業の神とされる
- ご利益:商売繁盛、大漁、家庭円満
- 主な神社:今宮戎神社、美保神社
猿田彦大神
- 読み方:さるたひこのおおかみ
- 誕生:天孫降臨の際に道案内をした神
- ご利益:道開き、交通安全、導きの神
- 主な神社:猿田彦神社、二見興玉神社
月読命
- 読み方:つくよみのみこと
- 誕生:伊邪那岐命の右目を洗った時に生まれた
- ご利益:厄除け、五穀豊穣、月の神格化
- 主な神社:月読神社
豊受大御神
- 読み方:とようけのおおみかみ
- 誕生:食物を司る女神、天照大御神の食事を担当
- ご利益:衣食住、産業繁栄
- 主な神社:伊勢神宮(外宮)
高皇産霊神
- 読み方:たかみむすびのかみ
- 誕生:天地開闢の最初に現れた造化三神の一柱
- ご利益:開運招福、縁結び
- 主な神社:サムハラ神社、天神社
天御中主神
- 読み方:あめのみなかぬしのかみ
- 誕生:宇宙の中心神、造化三神の筆頭
- ご利益:開運、安産、事業繁栄
- 主な神社:秩父神社、日高神社
木花咲耶姫命
- 読み方:このはなさくやひめのみこと
- 誕生:大山祇命の娘で火の中で出産した神
- ご利益:安産、火除け、子宝
- 主な神社:浅間神社、敷地神社
大山祇命
- 読み方:おおやまつみのみこと
- 誕生:伊邪那岐・伊邪那美の子、山の神
- ご利益:山の守護、海上安全、鉱山守護
- 主な神社:大山祇神社、三嶋大社
大山咋神
- 読み方:おおやまくいのかみ
- 誕生:山の地主神で農業神
- ご利益:方除け、厄除け、家内安全
- 主な神社:日吉大社、松尾大社
保食神
- 読み方:うけもちのかみ
- 誕生:食物を体から出して献上した神
- ご利益:五穀豊穣、食の安全
- 主な神社:外宮、稲荷神社系
思金神
- 読み方:おもいかねのかみ
- 誕生:高皇産霊尊の子、知恵の神
- ご利益:学業成就、知恵、発想力
- 主な神社:春日神社、意富布良神社
高龗神
- 読み方:たかおかみのかみ
- 誕生:水や雨を司る神、火の神を斬った際に誕生
- ご利益:祈雨祈晴、農業繁栄、水の守護
- 主な神社:貴船神社
市杵島姫命
- 読み方:いちきしまひめのみこと
- 誕生:宗像三女神の一柱、弁財天と同一視
- ご利益:芸能、財運、交通安全
- 主な神社:厳島神社、宗像大社
八幡大神(応神天皇)
- 読み方:はちまんおおかみ(おうじんてんのう)
- 誕生:第15代天皇、後に八幡神として信仰される
- ご利益:勝負運、出世開運、子育て
- 主な神社:宇佐神宮、石清水八幡宮
神功皇后
- 読み方:じんぐうこうごう
- 誕生:応神天皇の母、新羅遠征で神格化
- ご利益:安産、子宝、開運
- 主な神社:住吉大社、気比神宮
仁徳天皇
- 読み方:にんとくてんのう
- 誕生:第16代天皇、民を思う仁政で知られる
- ご利益:商売繁盛、健康祈願
- 主な神社:高津宮、難波神社
住吉三神
- 読み方:すみよしさんじん
- 誕生:伊邪那岐命の禊から生まれた三柱の神
- ご利益:海上安全、航海守護
- 主な神社:住吉大社
天穂日命
- 読み方:あめのほひのみこと
- 誕生:天照大御神の子、出雲に派遣された神
- ご利益:国土安泰、農業繁栄
- 主な神社:若狭彦神社、天穂日神社
大物主命
- 読み方:おおものぬしのみこと
- 誕生:大国主命の和魂とされる神
- ご利益:病気平癒、五穀豊穣、酒の神
- 主な神社:大神神社、金刀比羅宮
菊理媛神
- 読み方:くくりひめのかみ
- 誕生:伊邪那岐・伊邪那美の和解に登場する女神
- ご利益:縁結び、調和、仲裁
- 主な神社:白山比咩神社
このように、御祭神の種類は神話の神々だけでなく、実在した歴史的人物まで多岐にわたります。神社を訪れる前に、その神社の御祭神が誰であるかを調べておくと、ご利益への理解がより深まります。


